少人数チームのための“生成AI逆転マニュアル”

「人が足りない」「時間が足りない」「資料をつくる余裕なんてない」。
そうした声は、介護・医療・福祉などの“人中心の現場”ほど、日々の実感として多く聞かれます。
しかし、その“足りない”を逆手にとって、チームの力を拡張できるのが、今注目されている生成AI(Generative AI)の本当の魅力です。ChatGPTをはじめとするツールは、少人数チームの情報整理や業務効率化を、想像以上にサポートしてくれます。
私たちのチームでは、ChatGPTを活用することで、業務の整理や資料作成、記録の精度向上など、仕事の「手間」を減らす工夫を少しずつ進めています。
この記事では、現場で使える生成AI活用術を、初心者にもわかりやすく、実例を交えながら解説します。
なぜ“少人数こそ”生成AIと相性がいいのか
人が少ないからこそ、ひとりひとりの業務が重くなりがちです。 「マニュアルを整えたい」「記録をわかりやすくまとめたい」と思っても、どうしても後回しになってしまいます。
そこで役立つのが、ChatGPTのような生成AIです。
たとえば…
・口頭で伝えていた内容を文章に整える
・会議の議事録を要点だけにまとめる
・手順書のたたき台を作ってもらう
こういった作業を“ゼロから自分でする”のではなく、ChatGPTに「まずしてもらう」ことで、気持ちも時間もグッと楽になります。
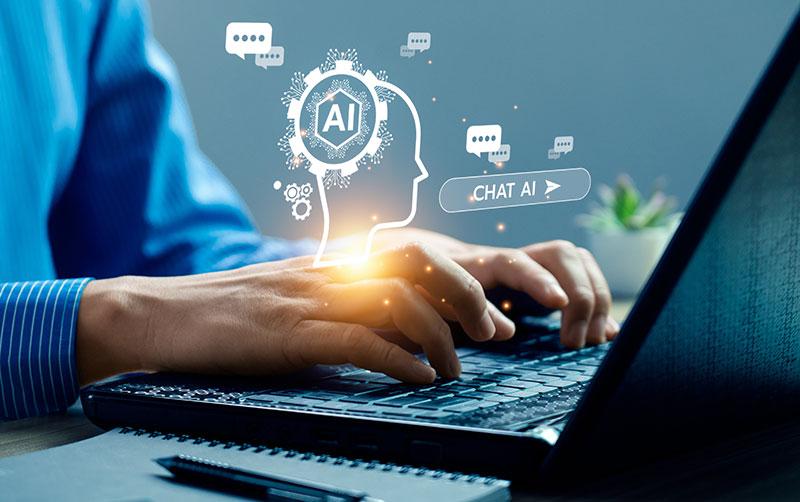
また、「どう考えればいいか分からない」ときに相談できる“相棒”としても活躍します。
さらに、生成AIの大きな魅力のひとつは、「指摘をされても感情的にならない」ことです。 上司や同僚から文面や業務について修正を求められると、どうしても受け取り方に気を遣ったり、時には気持ちが揺れることもあります。 でも、AI相手なら素直に「たしかに、こっちの方がいいかも」と思えるかもしれません。そんな使い方も、職場のストレスを減らす助けになります。
生成AIの性能は進化しても、私たちの“使いこなし”が要となる
ChatGPTなどの生成AIは、わずか数年で10倍以上の性能向上を遂げてきました。言語処理や要約力、アイデア生成のスピードは、専門家レベルに匹敵する領域に達しています。
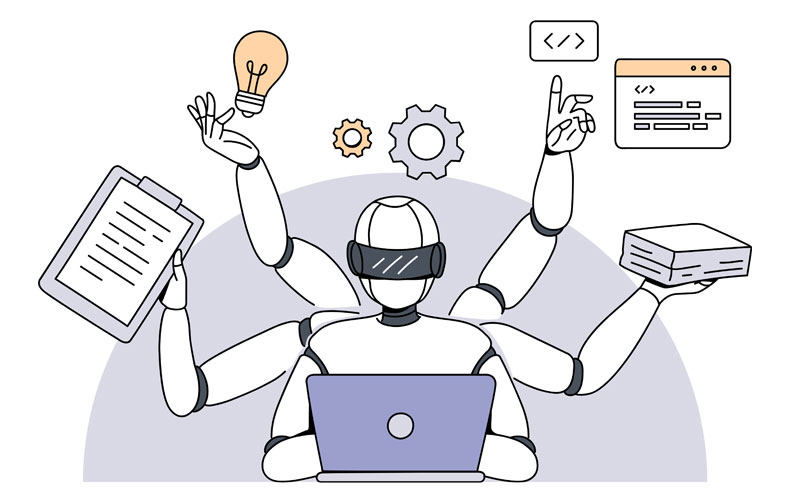
しかし、人間の情報処理能力は、そんなに急にはスケールしません。AIが10倍速くなっても、私たちの脳は10倍速で考えられるわけではないのです。
だからこそ、「たくさん返してくれる」AIよりも、「必要な情報を適切にまとめて返してくれる」AIが、現場では重宝されるようになっています。
生成AIを活用するカギは、問いの立て方(プロンプト)と出力結果の受け取り方です。どんなに賢いAIでも、質問がぼんやりしていれば、答えもぼんやりします。
未来の現場では、AIの操作スキルだけでなく、「AIとどう対話するか」が問われるようになります。生成AIを単なる便利ツールではなく、“共に考えるパートナー”として活用する力が、働き方そのものを変えるのです。
生成AIを活かす3つのポイント
1.「全部自動化しよう」としない
生成AIに任せるのは“下書き”や“整理”。最終的な判断は人が行うことで、安心して使える存在になります。
2.完璧を求めず、とにかく試してみる
最初はうまくいかなくても大丈夫。「こんな風に言えばいいんだな」と、触っていくうちに少しずつコツがわかってきます。
3.一部の職種だけで使わない
介護士さんも、事務の方も、相談員さんも。日々の仕事の中で「こうなったら便利だな」を感じた人こそ、AIを活かすチャンスがあります。
どの生成AIから始めるべき?
はじめての生成AIには「ChatGPT」がおすすめです。
理由は…
・返答がやわらかく、会話的で読みやすい
・操作がシンプルで直感的
・使い方の事例が豊富で学びやすい
・日本語でも高い精度で対応可能
他にもGoogleの「Gemini」やAnthropicの「Claude」などがありますが、日常的な業務で“会話ベースで使いたい”場合は、ChatGPTがもっとも親しみやすい選択肢です。

ChatGPTだけでできる、私たちの活用例
記録の文面チェック:「この文章、伝わるかな?」と相談
業務メモの要約:長いメモから必要なポイントを抜き出す
マニュアルのたたき台作成:作りたい内容を伝えると、ひな形が出てくる
職員向け案内文の下書き:「やわらかい言い方にして」とお願いする
ITが得意でなくても使えるのが、このツールの強みです。
少人数でも“回る仕組み”にするには?
小さく始めて、小さく共有
最初から全員でやろうとしなくて大丈夫。1人が「これ便利だったよ」と共有するだけでも、周りに広がっていきます。
プロンプト(質問)の書き方をシェア
「こう聞いたらうまく返ってきたよ」という質問例を残しておくと、他の人も試しやすくなります。
業務の流れを少しずつ見直す
AIが使える場面が見えてきたら、ちょっとずつ業務フローを調整していくと、もっと楽になります。空いた時間は、利用者さんとの関わりや、ゆとりある働き方にもつながります。

難しいことは要らない。まずは“触ってみる”
「おはよう」と話しかければ「おはようございます」と返してくれるAI。 そんな気軽さこそ、生成AIを始める第一歩です。
たとえば、
「今日の業務を簡単にまとめて」
「この文章、やさしい言い方にして」
「説明文を短くしてみて」
LINEでメッセージを送るような感覚でAIに話しかけるだけで、驚くほど実用的な答えが返ってきます。

おわりに
生成AIは、誰かの仕事を奪うための道具ではありません。 むしろ、今いる人たちが、もっと楽に、もっと自然に働けるようにする“補助輪”のような存在です。
人が少ないからこそ、試してみる価値があります。
まずは、「今日の業務、簡単にまとめて」とChatGPTに話しかけてみてください。
未来の介護・医療・福祉の現場を支える力になるのは、「使ってみた」その一歩からです。

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 情報システム部 部長(CTO)
システム開発や技術戦略の立案を担うCTOとして、2024年より現職。25年以上のエンジニア経験に加え、ITコンサルタントとして公共・医療・製造・介護分野の業務改善プロジェクトに多数携わる。 また、過去にはソフトウェア企業の取締役として事業推進を担い、経営視点を踏まえたシステム導入やDX推進に強みを持つ。現場と経営の両面から、持続可能な技術基盤の構築に取り組んでいる。

