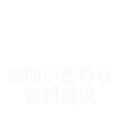社員が主役のDXストーリー ― 技術ではなく、人が会社を変えた ―

序章|このDXストーリーの始まりに
DX、AI、生成AI。
こうした言葉が日々ニュースを賑わせるようになって、もうかなりの時間が経ちました。技術は進化を続け、導入のハードルも下がり、多くの企業が何らかの形でデジタル変革に取り組む時代になっています。
一方で、「DXを導入したはずなのに、現場はあまり変わっていない」「ツールは増えたのに、社員は忙しくなる一方だ」という声も、決して少なくありません。技術が進んでいるのに、会社が本当に変わったという実感を持てない。そのギャップに、多くの現場が戸惑いを抱えています。
本来、DXとは「システムを入れること」でも「AIを使うこと」でもありません。働く人の行動が変わり、組織の文化が変わり、企業の未来が静かに更新されていく。その連続こそがDXの本質です。
そして、その変革の主役は、経営でもIT部門でもなく、日々現場で働く一人ひとりの社員です。ここから始まるのは、ある介護施設で実際に起きた、「社員が主役のDX」の物語です。
第1章|「また新しい仕組みが来るのか」というため息
その介護施設は、慢性的な人手不足と業務過多に悩まされていました。職員たちは利用者様にしっかり寄り添いたいと願いながらも、現実には記録、報告、情報共有、申し送りといった業務に追われる毎日を送っていました。
紙の書類とExcelが入り混じり、情報は人づてに伝わっていきます。ミスが起これば、現場の誰かが静かに責任を背負うしかありません。残業はいつの間にか当たり前のものになり、「忙しいですね」という言葉が、あいさつ代わりのように交わされていました。

そんなある日、上層部からDX推進プロジェクトの話が持ち上がります。会議室にその話題が出たとき、場の空気はどこか冷めていました。心の中には、「また新しい仕組みが入るのか」「どうせ現場は振り回されるだけだろう」という諦めにも似た感情が広がっていました。
過去にも電子化や新システムの導入は何度か行われてきました。しかし、その多くは現場の声とは切り離されたまま進められ、使いこなせない仕組みだけが増えていきました。画面の奥に眠ったままのシステムを思い出しながら、職員たちは今回のDXにも、期待より先に「どうせ同じだろう」という諦めを抱いていたのです。
第2章|プロジェクトの最初に変えたのは「IT」ではなく「問い」
ところが、このDXプロジェクトは、いつものパターンとは少し違った始まり方をしました。最初に開かれた会議で配られたのは、ツールの比較表でも、導入スケジュールでもありませんでした。
プロジェクトマネージャーが最初に取り組んだのは、現場の職員一人ひとりへの丁寧なヒアリングでした。日々のシフトの合間を縫って、小さな面談の時間がつくられていきます。
・どの作業が一番つらいのか。
・どこで時間が奪われているのか。
・どんな瞬間に「もう限界だ」と感じるのか。
最初のうち、職員たちはどこか遠慮がちでした。「忙しいのはお互いさまですから」「仕方ないですよね」といった言葉が口をついて出ます。それでも、何度か顔を合わせるうちに、少しずつ本音がこぼれ始めました。
記録業務の多さに、ふとため息が漏れる瞬間。申し送りの準備に追われて、利用者様のところへ向かう足が重くなる感覚。情報の行き違いが不安を生み、「本当にこれで大丈夫なのか」と胸の奥がざわつく夜。もっと利用者様と向き合いたいのに、それができないことへの悔しさ。
一つひとつの言葉には、積み重なった疲れだけでなく、諦めきれない思いがにじんでいました。

このヒアリングを通じて、プロジェクトはようやく「何を入れるか」ではなく、「何を変えるべきか」という問いから再スタートを切ることになります。業務の流れを一つずつ見直し、どこにムダがあり、どこで人が必要以上に時間やエネルギーを奪われているのかを洗い出していきました。
そのうえで、必要な部分にだけDXやAI、生成AIを組み込んでいきます。記録はデジタル化され、申し送りは音声入力と自動要約が支えるようになり、単純な事務作業はできる限り自動化されました。
しかし、このプロジェクトの中心にあったのは、「AIを使うこと」そのものではありませんでした。「人が本来向き合うべき仕事に、ちゃんと時間と心を使えるようにするには、技術をどう使うべきか」という問いでした。
現場の職員たちは、少しずつDXを違うものとして感じるようになっていきます。「これは上から降ってきた仕組みではなく、自分たちの声から生まれた変化なのかもしれない」。そんな小さな心境の変化が、現場の空気を静かに揺らし始めていました。
第3章|最初に変わったのは、業務よりも「現場の空気」だった
新しい仕組みが動き出してしばらくの間、数値上の劇的な変化はありませんでした。残業時間がいきなり半分になったわけでも、書類が一夜にして消えたわけでもありません。それでも、「何かが変わり始めている」という感覚だけは、現場に確かに広がっていきました。
申し送りでの混乱が、明らかに減っていきました。情報の行き違いが少なくなり、「あの件、聞いていません」という不安な一言が、以前よりぐっと減ったのです。記録のために残っていた職員も少しずつ減り、定時前後には「今日はここまでで大丈夫です」と仕事を切り上げられる日が増えていきました。
その変化は、会話の中にも表れました。以前は、すれ違いざまに交わす言葉といえば「今日も忙しいですね」がほとんどでした。それがいつの間にか、「今日は少し余裕がありますね」「さっき、利用者様とゆっくり話せました」といった言葉に変わっていきます。
仕事に対する感覚も、少しずつ変化していました。これまでは「決められた手順を、遅れないように、ミスをしないように、ひたすらこなすもの」だった業務が、「自分たちで改善していけるもの」へと姿を変えていきます。
ナースステーションや休憩室では、小さな不便に気づいた職員が「ここ、もう少し楽にならないかな」「これも変えられるかもしれないですね」と口にするようになりました。その声がプロジェクトメンバーへと届き、次の改善案が自然と生まれ、また現場に戻っていく。
DXは、いつの間にか「押し付けられる変化」ではなく、「自分たちで選び取り、育てていく変化」へと姿を変えていたのです。最初に変わったのは、業務の内容そのものではなく、「現場の空気」でした。

第4章|「AIに奪われる仕事」ではなく「AIと広がる仕事」
プロジェクトが始まる前、現場の多くの職員は、心のどこかで不安を抱えていました。AIや新しいシステムの話を聞くたびに、「自分たちの仕事はどうなるのだろう」「いつかは必要とされなくなるのではないか」という思いが、ふと頭をよぎることがあったのです。
誰かが声を大にして口にすることはありませんでしたが、その不安は確かに空気のどこかに漂っていました。
しかし、DXが進んでいくにつれて、現場が目の当たりにした現実は、こうした不安とはまったく逆のものでした。AIやシステムは、職員から仕事を奪う存在ではなく、「本当にやりたかった仕事」を取り戻していくための後押しになっていったのです。
書類作成や単純な入力作業に追われていた時間が少しずつ減り、その分、利用者様と向き合う時間が増えていきました。ある職員は、「以前は記録に追われて 『会話のための会話』 すらできなかった方と、最近は『その人の昔話』をゆっくり聞けるようになった」と話します。別の職員は、「ケア内容を振り返って『もっとこうしたらいいかも』 と考える余裕ができた」と振り返りました。
ミスが起きたときの捉え方も変わっていきました。これまでは、ミスが見つかると、心の中で「誰が悪いのか」を探してしまいがちでした。しかし、DXが進むにつれて、会話の焦点は「なぜこのミスが起きたのか」「仕組みとしてどう防げるか」へと移っていきます。個人を責めるのではなく、プロセス全体を見直す文化が、少しずつ根づいていきました。
AIは、人間の代わりに黙々と仕事をこなす“無機質な存在”ではなく、人が本来の力を発揮するための“伴走者”のような存在として、現場に静かに溶け込んでいきました。「AIに奪われる仕事」ではなく、「AIと一緒に広がっていく仕事」。職員たちの仕事観は、そんなふうに変化していったのです。

第5章|成果は、まず「人」に現れた
導入から半年ほどが過ぎたころ、数値としての変化も、目に見える形で現れ始めました。残業時間は着実に減っていました。業務の処理速度は上がり、情報共有にかかる時間も以前より短くなっていました。利用者様やそのご家族から寄せられる声も、「きちんと情報が伝わっている安心感がある」といった前向きなものが増えていきます。
しかし、経営陣が最も価値を感じたのは、そうした数値以上に、「人の変化」でした。
職員たちの表情は、以前よりやわらかくなっていました。会議の場でも、「こういう改善をしてみたら、うまくいきました」「次はここを変えてみたいです」と、自分たちの取り組みを誇らしげに語る姿が増えていきます。日常の何気ない会話の中でも、「もっとこうできるかもしれない」「この機能をこう使えないかな」といった前向きな提案が自然に行き交うようになりました。
DXは、単なる業務効率化のプロジェクトではなく、職員一人ひとりの自己効力感を高め、組織の空気そのものを変えるきっかけになっていました。変わったのは、システムの画面だけではなく、「ここで働きたい」「この現場を良くしていきたい」という人の気持ちだったのです。

終章|DXの主役は、これからも「人」であり続ける
このプロジェクトが教えてくれたのは、とてもシンプルな真実でした。DXも、AIも、生成AIも、それ自体が会社を変えるわけではありません。大切なのは、それをどう使うのか、誰のために使うのか、そしてどう現場とつないでいくのかという問いに向き合うことです。
この介護施設は、最先端の技術を次々と導入する『派手な先進企業』になったわけではありません。むしろ、これまで当たり前だった日常や業務とじっくり向き合い、社員一人ひとりが変化を「自分ごと」として捉え、動かしていける組織へと変わっていきました。
それこそが、DXが本当に目指すべき姿なのだと思います。技術はあくまで手段であり、主役はいつも「人」です。現場で働く一人ひとりの思考と行動が変わるとき、組織の文化が変わり、企業の未来が静かに書き換えられていきます。
私たちは今、DXとは「社員が主役になれる物語づくり」であり、その物語の中心にいるのは、他の誰でもない現場の人たちなのだと、確信しています。
おわりに|答えは、すべて現場にあった
このDXストーリーを書きながら、ふと一冊の本が頭に浮かんでいました。先輩に勧められて手に取った『THE GOAL*』です。
赤字続きで倒産寸前の工場を任されたのは、特別なカリスマ経営者ではなく、どこにでもいる中間管理職の工場長アレックスでした。彼が向き合っていた工場も、決して特別な存在ではありません。日本中のどこにでもありそうな、「ごく普通の会社」でした。
物語の前半で、アレックスも多くの企業と同じように「最新設備の導入」に活路を求めます。しかし、期待したほどの成果は出ません。打開策を求めて試行錯誤を重ねるうちに、彼はあることに気づきます。問題は設備の古さや新しさではなく、「一部の工程だけが極端に詰まっている」という、ごく現場的で具体的な事実だったのです。
すべてが悪いわけではない。ボトルネックは、現場のごく一部に集中している。
彼が本当に変えたのは、設備そのものではなく、ものごとを見つめる「思考」でした。
今回の介護施設のDXも、構図はまったく同じでした。高機能なAIやシステムが、魔法のように組織を変えてくれたわけではありません。業務のどこが詰まっているのか。誰が本当につらい思いをしているのか。何が最も時間と心を奪っているのか。その問いを現場に投げかけ、現場の声に耳を傾け、現場の知恵を信じたこと。そこからすべてが始まりました。
DXとは、最新技術を導入するイベントではなく、現場に眠っていた「改善の答え」を、テクノロジーという形で実装していくプロセスなのだと思います。そして、その変革を動かすのは、どこにでもいる社員であり、どこにでもいる管理職です。
『THE GOAL』が示した真理は、今のDXにもそのまま当てはまります。
答えは、いつの時代も、現場にあります。
そして企業を本当に変えるのは、システムではなく、人の思考なのです。

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 情報システム部 部長(CTO)
システム開発や技術戦略の立案を担うCTOとして、2024年より現職。25年以上のエンジニア経験に加え、ITコンサルタントとして公共・医療・製造・介護分野の業務改善プロジェクトに多数携わる。 また、過去にはソフトウェア企業の取締役として事業推進を担い、経営視点を踏まえたシステム導入やDX推進に強みを持つ。現場と経営の両面から、持続可能な技術基盤の構築に取り組んでいる。