未来の介護サービス提供への模索

株式会社エクセレントケアシステム執行役員(「品質管理部」)の坂本と申します。EX Magazineを担当するようになって3回目の掲載となります。これまでは、福祉サービスの品質管理や福祉サービスの質向上の根底となる社会福祉に対する私なりの考えや取り組む姿勢について述べるとともに、前回はその1つとしての介護サービスはかけがえのないものであり、私たちはその唯一無二のサービスにそれぞれの思いをのせて提供させていただいていることを、当社各施設・事業所の具体的な社会貢献活動を紹介しながら説明してきました。ご覧になられていない方は、第1回目から順にご覧いただければと思います。
今回は、介護サービスの品質を維持、向上させるための品質管理部の活動をご紹介させていただきます。
品質管理部の立ち上げとこの1年間
当社品質管理部は、本コラム第1回で述べたように、2024(令和6)年4月に新設され1年3ヶ月が経過しました。これまで、「品質管理方針」や「品質管理規程」の策定、会議・委員会や各種研修の整理など運営基準に関する内容、入職時の教育の指針となる「新入職員の手引き」を更新しました。ご存知の通り、「2025年問題」を見据え、2024(令和6)年4月、介護保険制度は大幅な改正がなされるとともに、同年は介護報酬の改定や介護保険事業計画の更新に留まらず、医療計画の更新と診療報酬の改定が重複するという6年に1回の大改正の時期でした。それに対応するため、現場職員が安心して利用者やその家族のための介護サービスの提供に集中して取り組めるよう、品質管理部では今回のこれらの更新を含め、継続的に規程やマニュアル、その他施設・事業所として成り立つために当然守らなければならない部分(「品質の保証(Quality Assurance)」)の整備を進めていきましたし、今後も永続的に進めていく予定です。

一方、他の施設・事業所よりも優れた部分(「サービスの質(Quality Improvement」)の整備については、当社の品質に関する三本柱の1つである「接遇」に関し、利用者やその家族、その他お客様に対して失礼のない対応ができているか、必要最低限の接遇について現地調査を実施する仕組みを整備しました。その結果から、場合によっては個別指導や研修を直接現地やzoomを使用して行うとともに、必要最低限の接遇ができている職員に対しては、よりレベルアップを求める研修を開催してきました。今後は、実際に現地調査を行った施設・事業所の継続的なフォロー(各施設・事業所に設置されているサービス向上委員会に接遇の評価を含めたPDCAサイクルの持続的運用)ならびに、よりレベルの高い接遇の実施に向け、検討して参りたいと思っています。
また、当社の品質に関する三本柱の1つである「食事」では、当社で扱う食事の内容と形態を整理し、品質の標準化の足がかりとしました。また、前述の接遇の現地調査に加え食事についても今年度から実施しています。現時点では、地域密着型共同生活介護(グループホーム)で行っている自社調理を中心に、設備の整備やメンテナンス、調理方法や衛生面への配慮など、単に現地で職員に指導するだけでなく悩みや相談について、いつでも受け付ける体制を整えています。また、本コラム第2回でご紹介した「もぐカフェ(子ども食堂)【エクセレント修学院/京都市】」に、品質管理部の食事指導員がその中心的役割として参加し、社会連携・社会貢献活動の新しい形を模索し、社会連携・社会貢献活動と「食事」との相乗効果とその可能性について挑戦しています。今後は、それら活動(もぐカフェ(子ども食堂))以外も含め、その平準化を図り、介護サービス品質の一翼を担えるよう努力していきたいと考えています。


その他にも、介護サービス品質という目に見えにくいものを見える化するための様々な方法として、品質に関する広報活動の強化や利用者・利用者家族満足度調査の強化を検討しているところです。これらについて、後の回に譲りたいと思います。
品質管理部の位置づけと立場
ところで、「品質管理部」の役割は、品質の保証と質の向上とひとことで言えますが、その範囲は多岐にわたります。すなわち、「品質の保証」のためには、各施設・事業所のサービスの平準化が求められます。そうなると、それらの指針となる各規程・マニュアル・ガイドラインの標準化が求められるのは当然ですが、それら規程やマニュアル、ガイドラインは、弊社総務部や情報システム部との連携が欠かせません。また、「接遇」や「食事」の指導や質向上のためには、前述の現地調査に加え、日頃の職員教育や研修機会の確保が求められます。したがって、弊社人材開発部との連携が必要となってきます。
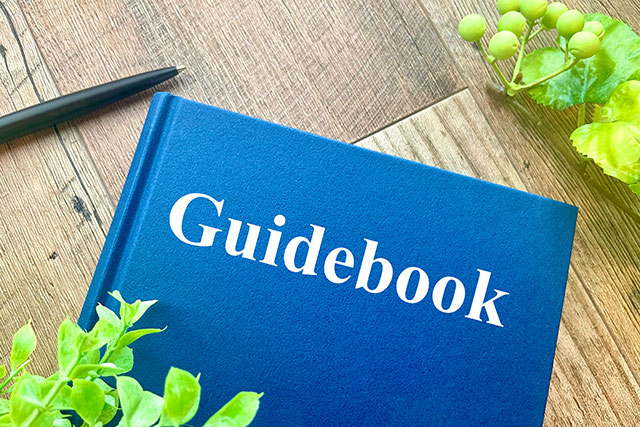
また、新しい取り組みとして充実させようとしている社会連携・社会貢献活動については、各施設・事業所の管理者の力量を前提に、場合によっては当社を代表する立場として、それら活動に関わって頂いている同業法人や団体、地域住民と連携する必要があるでしょう。このように、「品質管理部」メンバーは、ひとり一人が様々な領域の把握と興味、広い視野を持つ必要があり、そのことを常日頃から意識するようにしています。とりわけ、本コラム第1回で述べたように、「・・・一問題に焦点をあてるのではなく、それらに関わる人々の生活全体をみて行動できるような人間、・・・」が求められていると考えています。そして、各施設・事業所の現場職員が主人公であることを前提に、彼ら・彼女らを支える存在であり続けたいと思います。
品質向上に向けたプロジェクトの立ち上げ
弊社ホームページにある通り、2025(令和7)年度は「不確実な社会への挑戦 -安定と継続的な介護サービスと生活支援を目指した7つのプロジェクト-」をテーマに、7つのプロジェクトが立ち上がりました。詳細はホームページをご覧になっていただければと思いますが、解説文にあるとおり、弊社スーパーバイザー、エリアマネジャー、各部の執行役員がメンバーとなってVisionである「オンリーワン オンリーユー」を実現するための土台を創りのため、メンバーとしてプロジェクトの成功のため日々邁進しています。
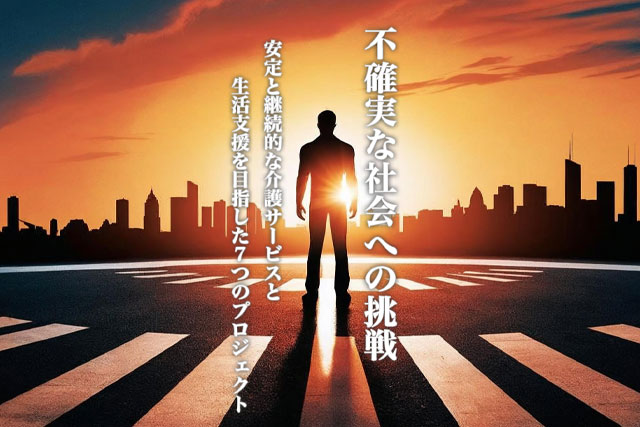
-安定と継続的な介護サービスと生活支援を目指した7つのプロジェクト-
ご承知の通り、プロジェクトは決められた期限と予算の中で、決められた目的とそれを実現するための計画に沿って活動することであり、より専門的な職員で構成されます。各プロジェクトで設定された目的の実現は当然のことですが、これら7つのプロジェクトが協力し合ってテーマにある「介護サービスと生活支援をこの不確実な社会で安定的に、継続的に実施」することが求められます。したがって、プロジェクトメンバー個々は専門性の高い同プロジェクトメンバーの活動を尊重しつつ、プロジェクトリーダーはそれらをまとめ、最適解を目指す必要があります。この活動には、まさに前述の「ひとり一人が様々な領域の把握と興味、広い視野を持つ必要があり、そのことを常日頃から意識する」が役立つことは当然の帰結と言えます。
品質に関する中・長期計画と事業計画の策定
このように、品質の保証と質の向上は、各施設・事業所の職員、同業法人や団体、地域の住民、各部の執行役員やスーパーバイザー、エリアマネジャーなど多くの方が協力し合い、共感し、尊重し合い始めて実現できるものです。「ローマは一日にしてならず」という慣用句があるように、品質の向上には毎日の努力の積み重ねが必要であり、私自身は社会福祉で特に重要な人対人の細かなコミュニケーション一つ一つの積み重ねが重要であると思っています。したがって、それらを着実に進めるため、「品質管理部」では、“Qrossroad”Quality×Crossroad -品質と“これから”がつながる交差点(クロスロード) ここから、未来を描く歩みが始まる。-と題した中長期ビジョンと品質戦略の方向性を作成しました。是非ご覧頂き、ご感想をいただければ幸甚です。

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 品質管理部 部長
川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 非常勤講師、川崎医療福祉大学大学院 医療福祉マネジメント学研究科医療秘書学専攻 非常勤講師、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟国家試験合格支援委員会委員(科目幹事)、公益社団法人岡山県社会福祉士会担当理事、第三者評価委員会委員(評価調査者・事務担当)、一般社団法人日本レセプト学会理事、社会福祉法人弘徳学園評議員、NPO法人晴れ アドバイザー
病院の事務、通所介護の生活相談員を経験、川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部医療福祉経営学科副学科長を経て、2024年より現職。福祉サービス第三者評価の評価調査者を担っている。医療福祉制度に関する学術論文多数発表。分担執筆『障がい福祉のすすめ』第5章(学文社)などの著書もある。川崎医療福祉大学創立30年記念「未来の医療福祉のあたり前を考える」論文部門最優秀賞受賞。博士(社会福祉学)・修士(社会学)ともに佛教大学、社会福祉士。

