介護現場の透明化と信頼構築④-福祉サービス第三者評価で実現する「質の高いケア」-
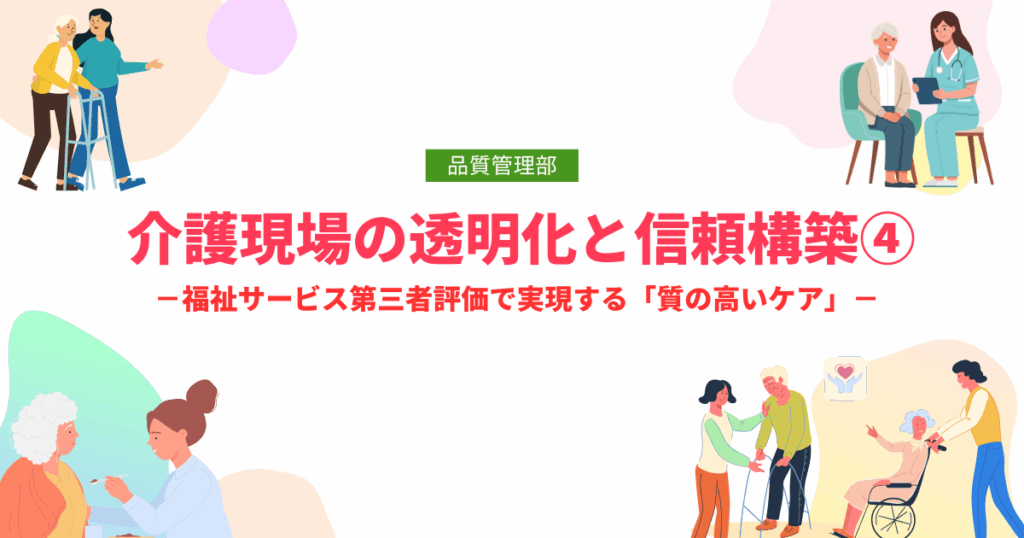
株式会社エクセレントケアシステム執行役員(「品質管理部」)の坂本と申します。EX Magazineを担当するようになって7回目の掲載となります。今まで6回にわたって、介護現場の透明化と信頼構築を実現するための方法の1つとして昨今注目を集めている「福祉サービス第三者評価」の考え方やその仕組みについて取り上げております。今回は、その4回目です。(第1回目の記事はこちら)
前回は、「福祉サービス第三者評価」の中で最も大切な評価基準について、我々が受審することによってなぜ福祉サービスの質向上が図れるのか、その仕組みの根幹である評価基準の改定について概観しました。「評価基準の改定内容≒国が社会福祉(介護)施設・事業所求めていること、求めようとしていること」が確認できたと思います。
それを受け、昨今大きな改定となった2018(平成30)年改定*1の内容について確認したいと思います。
改定された評価基準について
2018(平成30)年の改定では、8項目の評価基準が改定されました。今日は、その前半部分を概観します。
●理念、基本方針が明文化され周知が図られている。
共通評価項目の最初に示されている評価基準であり、報告書をみた際、最初に目が行く項目となります。今回の改定では、前回の例でお示ししたように理念や基本方針に関する3つの評価基準が統合されました。具体的には、職員への理解と周知の徹底がより明確になるとともに、評価対象の施設・事業所のみならず、法人の理念と基本方針にまで範囲を拡大して評価することになりました。また、理念、基本方針の内容について改定されるか否かではなく、昨今の社会情勢や社会福祉政策の動向を加味した定期的な見直しを検討する機会を設けているかが問われるようになりました。
●中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。
施設・事業所にとって、3〜5年程度を期間とした中・長期計画の策定は必須です。とはいえ、評価調査者を長年務めてきた筆者にとって、中・長期計画が策定されている施設・事業所は、増えてきたとはいえまだまだ少なく「c」評価にせざるを得ない場面が多々見られます。ましてや、達成度を測るための具体的な数値などの明示がされていないケースが見られています。そのような中、今回の改定では経営環境等の把握・分析結果を踏また中・長期計画の策定、理念や基本方針の具現化を図るための中・長期計画の策定となっていることが必要であることが明示されました。
一方、公立施設については、管理者に与えられた職掌の範囲を考慮したうえでの評価の実施であるとされ、中・長期計画は施設・事業所の枠を超えた地方自治体単位で策定される計画で代用されるとしました。
●公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。
内部監査や苦情解決処理に関する手順とその組織的運営などについては、当初より評価項目の1つとして位置づけられていました。ところが、「会計監査人」の設置が義務化されました。そのような中、今回の改定では会計監査または公認会計士、監査法人、税理士もしくは税理士法人が実施する財務管理、経営管理、組織運営・事業等に関する指導・助言その他の専門的な支援による取組が明文化され、その実態について評価することになりました。
●地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。
施設・事業所をとりまく地域の福祉ニーズを把握することは、地域に開かれた施設・事業所を目指すうえで、また、その地域に施設・事業所が存在する意義や価値を見出すうえで大切なことであり、当初から評価項目に設定されていました。そのような中で、今回の改定では「地域社会」を明文化し、地域の福祉ニーズに応えているかを評価することになりました。つまり、評価施設として、ターゲットとしている地域社会とは何か、明確にしたうえでニーズ把握しているかということが大切といえます。また、評価施設内で対応できない利用者ニーズを地域社会でどのくらい対応できているか把握する活動についても評価すると同時に、その取組は、法人としての取組も評価の範囲に含めるとしました。つまり、様々な社会資源と地域連携し利用者のニーズに対応しているか、また、同一法人内の連携による対応もその範囲に含まれます。
●地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。
この評価項目は、新しく設定された評価項目です。地域の福祉ニーズの把握については、前述の評価項目で確認することになります。そして、地域の福祉ニーズに「等」が付くことにより、施設・事業所は福祉サービスに特化した活動ではなく、公益的事業の実施が評価されます。したがって、上記実施の前提は、地域ニーズの把握であり行政からの助成による実施ではなく、法人や施設・事業所の資産等を活用した追加のサービス(自らもっている知識、技術、価値を提供)をこの項目で評価します。
評価項目の内容と今後の方向性
今回は、2018(平成30)年の評価基準改定について、紙面の関係上一部をご紹介しました。繰り返しになりますが、今回の改定を詳細に分析すれば、国が施設・事業所に求めている内容をいち早く確認することができ、施設・事業所としての今後の方針や方向性を立てやすくなります。次回は、残りの評価項目の改定内容と「福祉サービス第三者評価」の未来について述べたいと思います。
<脚注・参考文献>
*1 厚生労働省(2018)『「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について」の一部改正について』

株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 品質管理部 部長
川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 非常勤講師、川崎医療福祉大学大学院 医療福祉マネジメント学研究科医療秘書学専攻 非常勤講師、一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟国家試験合格支援委員会委員(科目幹事)、公益社団法人岡山県社会福祉士会担当理事、第三者評価委員会委員(評価調査者・事務担当)、一般社団法人日本レセプト学会理事、社会福祉法人弘徳学園評議員、NPO法人晴れ アドバイザー
病院の事務、通所介護の生活相談員を経験、川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部医療福祉経営学科副学科長を経て、2024年より現職。福祉サービス第三者評価の評価調査者を担っている。医療福祉制度に関する学術論文多数発表。分担執筆『障がい福祉のすすめ』第5章(学文社)などの著書もある。川崎医療福祉大学創立30年記念「未来の医療福祉のあたり前を考える」論文部門最優秀賞受賞。博士(社会福祉学)・修士(社会学)ともに佛教大学、社会福祉士。

