第3章 介護現場マネジメントの方法⑬【マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~】
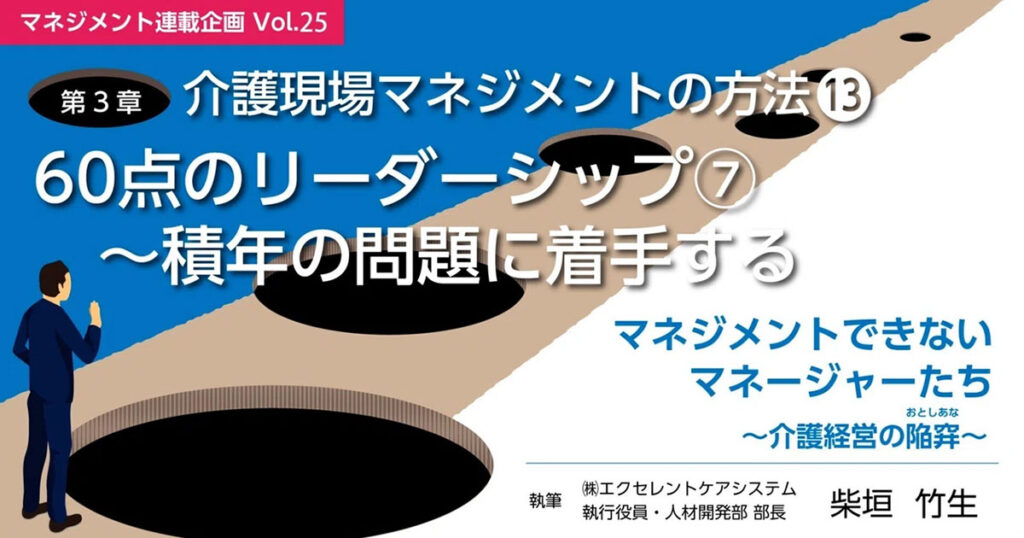
本記事は、人材開発部によるマネジメント連載企画「マネジメントできないマネージャーたち ~介護経営の陥穽(おとしあな)~」のVol.25です。(Vol.1から読み始める場合はこちら)
60点のリーダーシップ⑦ ~積年の問題に着手する~

竜退治に挑む
竜退治で村人の信頼を得るのは、何も小説やゲームの中だけの話ではない。たとえば、赴任先の事業所にも「竜」はいる。古今東西の竜退治物語が王子や青年の通過儀礼の意味合いを持つように、新任管理者にとってもそれは新しい職場に受容されるための試金石となる。
介護事業所に「竜」は数多く存在する。黙ってサービス残業を繰り返す職員、職場のルールを守らない職員、業務上の命令違反を繰り返す職員、協調性がなさすぎる職員、感情的になることが多い職員、実質的な支配力を持ちながら公には何ら責任をとらない裏ボスの存在などがそれにあたる。故障したまま放置された機器類、現場が必要と考えている備品購入の棚上げ、ずさんな金銭管理・在庫管理、慢性的な介護保険関連帳票の不備なども竜の仲間だ。
以前、本連載の目標設定の回で「法人が求める職場の姿」として、離職率抑制、事故防止、業績向上をあげたが、いわばあれが法人の望む竜退治で、上記のこれらが現場の望む竜退治ということになる。
法人の望みと現場の望みは密接な関係にある。現場の問題を解決することで、法人の目標が達成されることも少なくない。竜退治は、事業面の目標達成のためにも、責任者としての通過儀礼をクリアするためにも、挑む価値が高い。赴任したらすぐに着手すべきだ。

竜退治のセオリー
竜退治の物語はだいたい次のように進む。
①旅の騎士が訪れた村で竜の悪行を耳にする。
②騎士は村人たちから聞いた竜の居場所に出向き見事竜を退治する。
③騎士は村へ帰還し受け入れられる。
この流れは、介護事業所の竜退治にもそのまま援用できる。
まずは職員たちへのヒアリングである。職場で困っていること、問題だと思っていることを面談で聞きとっていくわけだが、すべてを真に受けないよう注意が必要だ。物語世界で竜がすることは万人にとっての「悪行」に決まっているが、ヒアリング時に職員たちが口にする「悪行」は必ずしもそうとは限らない。主観的な意見や個々人の複雑な思惑が入り混じるため、複数の意見から総合的に判断する必要がある。また、問題の種類が多い場合は、優先順位をつけて対処していくことになる。
次に退治だが、これも聖剣でバトルというわけにはいかない。ただ、積年の問題というものは、前任者が手を焼いてきたからそうなっているのであって、対処するにはそれくらいの覚悟がいるのは確かだ。管理者の竜退治とは、平たくいえば「職員にいいにくいことをいうこと」である。つまり、闘う相手は問題を引き起こしている職員のように見えて、実はそうではない。真の敵は自分なのだ。だから、竜退治は通過儀礼(イニシエーション)なのである。
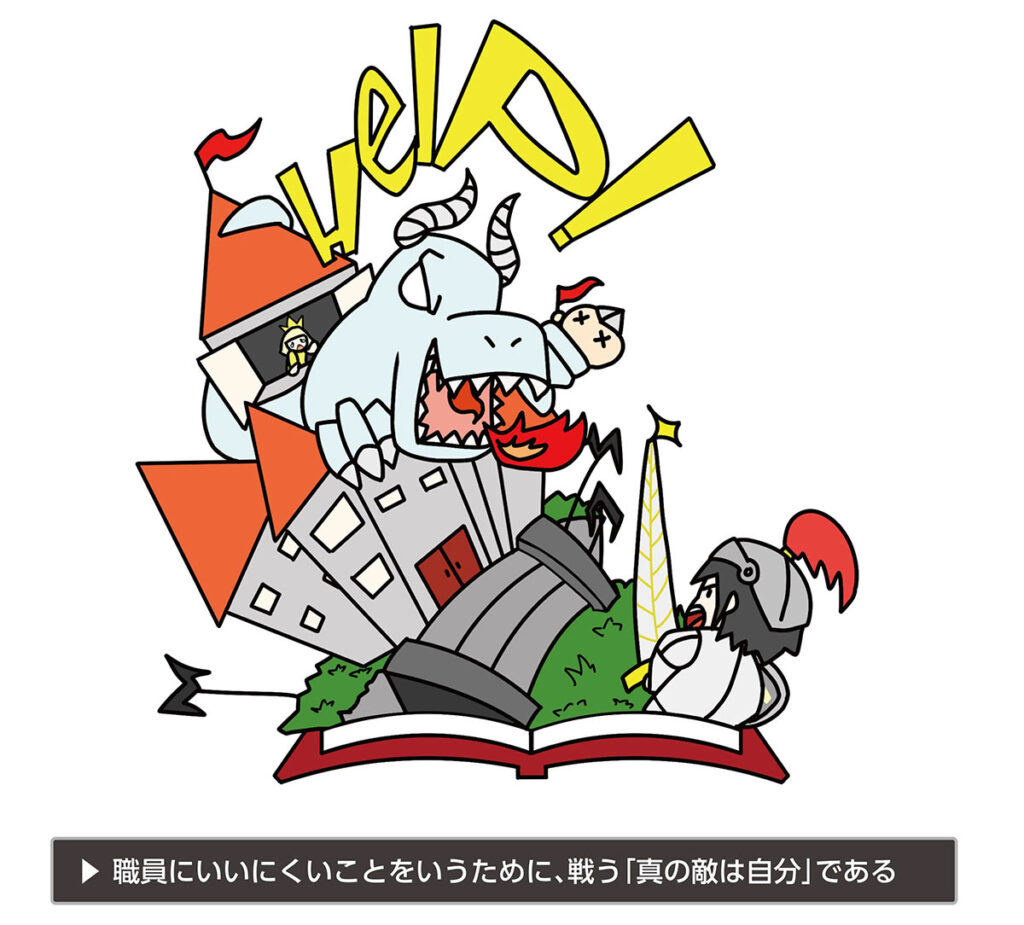
能力よりも尽力
労務上・業務上の約束事を守らない者たちへの注意は、はっきりいって億劫だ。協調性のない職員や感情的になりやすい職員への説教も、できればしたくない。ましてや裏ボスに配置転換の話をすることなど避けて通りたいのが本音だろう。機器の修理や新たな備品購入の稟議をあげて経費が嵩む話を上司とするのも、不備だらけの帳票類を整備するのも、気が重い。
だが、それをあなたが実行するのかどうか、職員たちは黙って見ている。彼ら彼女らは、管理者が代わったときが積年の問題を解決するチャンスであることを知っている。あなたがそのことに気づいているのか、いないのか。気づいていながら、気づかぬふりをしているのか。本気で問題解決に取り組む気持ちがあるのか、ポーズだけなのか。見きわめようとしているのだ。
結果的に、解決できる問題は少ないかもしれない。それでも、解決しようとする姿勢自体を職員たちは評価してくれることだろう。もちろん問題は解決できた方がいいが、それ以上に、彼ら彼女らにとっては、新しいリーダーが自分たちのために働いてくれるかどうかが重要なのだ。
村の住人たちは竜退治の結果がすべてだが、介護事業樹の住人たちはそのプロセスも見た上で、竜退治から帰還した管理者を受け入れてくれる度量がある。チャレンジしないのはもったいない。まず大事なのは、問題解決の能力よりも、問題解決への尽力なのである。


株式会社エクセレントケアシステム 執行役員 / 人材開発部 部長
兵庫県立大学大学院経営研究科(MBA)講師、公益財団法人介護労働安定センター 雇用管理・人材育成コンサルタント、大阪市モデル事業「介護の職場担い手創出事業」アドバイザー、日本介護経営学会会員
1966年大阪府生まれ。大手生命保険会社勤務を経て、1999年に介護業界に転じ、上場企業および社会福祉法人において数々のマネジメント職を歴任。2019年より現職。マネジメントに関する講演実績多数。近著に『老いに優れる』(社会保険研究所)、『介護現場をイキイキさせるマネジメント術』(日本ヘルスケアテクノ)がある。

